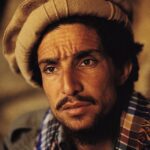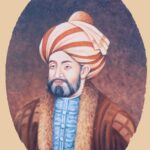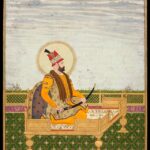ソ連軍の動きと撤退への道程
ソ連軍の戦略とその失敗
1979年12月、ソ連軍はアフガニスタン民主共和国を支援する目的で本格的な侵攻を開始しました。アフガニスタンを「友好国」としてソ連圏の一部に組み込むことが目的でしたが、その背後には地政学的理由もありました。アフガニスタンは南アジアと中東を結ぶ戦略的な要衝に位置しており、そこを押さえることで地域全体への影響力を強めようとしたのです。
しかし、ソ連軍はすぐに予想外の困難に直面しました。ムジャヒディンを中心とした反政府武装勢力は、ゲリラ戦術を採用してソ連軍に激しい抵抗を見せました。地元の地形や気候に精通したムジャヒディンは、有利な山岳地帯を拠点に戦いを進め、近代装備を持つソ連軍に大きな損害を与えました。ソ連軍は数々の掃討作戦を試みましたが、ムジャヒディンの柔軟な戦術の前にほとんど成功を収めることができませんでした。この戦いは次第に泥沼化し、「ソ連のベトナム戦争」とも呼ばれるようになります。
軍事作戦の課題とコスト
ソ連軍の軍事作戦は、莫大な人的・経済的コストを伴いました。10年間にわたる紛争で数万名のソ連軍兵士が戦死し、数十万名が負傷したとされています。また、戦争を支えるための経済的負担はソ連国内の財政に大きな影響を与え、次第に国内の不満を高めました。
戦場においても課題は山積していました。アフガニスタンの険しい山岳地帯や広大な砂漠地帯は、機械化部隊や航空支援を要するソ連軍にとって極めて厳しい環境でした。さらに、反政府勢力にアメリカやパキスタンなどの国際的な支援が行われていたことも、ソ連軍の苦戦を助長する要因となりました。特に、ムジャヒディンに提供された携帯型地対空ミサイル「スティンガー」は、ソ連軍の航空優勢を脅かし、作戦行動をさらに困難にしました。
ジュネーブ合意に基づく撤退

1980年代後半、戦争の長期化による負担と国際的な圧力に直面したソ連は、アフガニスタンからの撤退を模索するようになります。当時、ソ連の指導者となったミハイル・ゴルバチョフは、紛争の「解決」を優先事項とし、外交交渉を進めました。
1988年、国連の仲介のもとでジュネーブ合意が締結され、ソ連軍の完全撤退が規定されました。この合意の中では、アメリカとソ連がそれぞれアフガニスタンの関係者への軍事支援を停止することも含まれていましたが、特にムジャヒディンへの支援が完全に止まることはありませんでした。ジュネーブ合意は一定の外交的成功とみなされますが、実際にはアフガニスタン内の対立や内戦を完全に終わらせるものではありませんでした。
撤退がもたらした影響

ソ連軍は1989年2月にアフガニスタンから完全撤退しました。これにより、ソ連の直接的な介入は終わりを迎えましたが、アフガニスタンの内戦は依然として続きました。特に、ムジャヒディンの各派閥の間での権力争いが激化し、アフガニスタンはさらなる混乱へと突入することになります。ソ連撤退後の数年で共産党政権も崩壊し、国家は無政府状態に近い状況となりました。
ソ連崩壊への影響と冷戦の転換点
ソ連がアフガニスタンから撤退したことは、国内外に大きな影響を及ぼしました。アフガニスタンでの敗北はソ連内部の政治的混乱を深め、経済の低迷や国民の不満をさらに増大させました。これが1991年のソ連崩壊に至る一因となったと考えられています。同時に、アフガニスタン戦争は冷戦構造における転換点ともなり、西側諸国が「共産主義の拡張」を抑え込む成果として評価されました。この戦争は、冷戦期の地政学的争いの象徴として、その後の国際政治にも深い教訓を残しました。